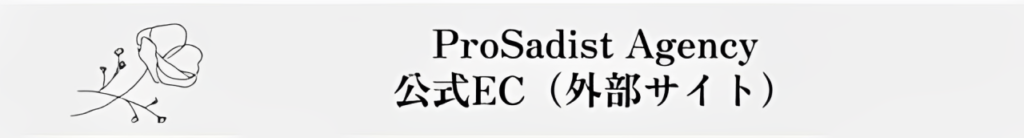特別公開
ProSadist Agencyオープンを記念して、プロデューサーDr.N監修のSM短編小説集「わたしを連れて行ってくれた彼は」の一部作品を期間限定で特別公開いたします。

ProSadist Agencyの公式オンラインショップからご購入いただけます。(ダウンロード版)
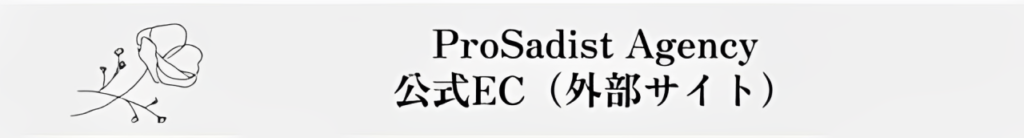
目次
Episode 1 再生
Episode 2 知欲
Episode 3 証明
Episode 4 克服
Episode 5 勝利
Episode 6 克己
Episode 7 救済
Episode 8 門出
Episode 9 情愛
Episode 1 再生
「申し訳ないんだけど、キャミソールは着ていてくれるかな」
恋人からそう告げられた時、何を言われたのかわからず、身体が一瞬固まってしまった。
恋人が、どこかばつの悪そうな表情を浮かべていること。そして、その目線が裸にタオルを巻いて脱衣所から出てきたわたしの「胸」に向けられていることを確認して、意図を理解した瞬間、足元がぐらりと揺れた気がした。
「それは……わたしの身体を見たくないってこと?」
「悪いけど、萎えそうだから」
そんなことを言うなんて、ひどい。
非難しようとして思い留まったのは「萎える」の気持ちではなく、ペニスを指している――恋人はEDという醜態を晒すことを恐れている――ことに気が付いたからだった。
なんて、正直な人なのだ。
けれども、その正直さがわたしを傷つけることには、思い至らなかったのだろうか。
「……ごめん。なんか、わたしのほうが萎えちゃった。今日は帰る」
わたしは恋人にそう告げると、再び服を着るために、脱衣所へ引き返した。
***
乳がんを患って左胸の膨らみを失ったのは、ちょうど一年前。二十九歳の時だった。
まだ十分若いし、結婚だってしていない。それなのに片方の乳房を失くしてしまったわたしは、術後、世界の終わりが来たかのように悲しみに沈んでいた。
けれども、実際に世界が終わることはなく、日常は淡々と続いていく。
ならば、生きていくしかない。どうせ生きるなら、前を向いて進みたい。
そう決心し、ずっとそばで闘病生活を支えてくれていた恋人に「セックスをしたい」と思い切って打ち明けた。
恋人は「実は、もう君を抱けないのかと思って、諦めていた」と予想以上に喜んでくれたし、そのために、とわざわざ都心のシティホテルの予約までしてくれた。それが今夜だった。
肉体の傷と異なり、心に受けた傷は目に見えず、終わりも見えない。
恋人とは結局上手くいかず、ホテルでの出来事から間を置かずに別れることとなった。
あの日を境に、すっかり思いは冷めていた。けれども、それまでずっと心の支えになってくれたことは確かだったから、恋人を失くして心にぽっかりと穴が開いたようだった。
何かでそれを埋めなくては、とても生きていけそうになかった。
わたしは、必死にやりたいことを考えた。
そうして思いついたのが「SMがしたい」ということだった。
ただでさえ傷ついてボロボロのわたしが、さらに傷つけられることを願うなんて、一見おかしいだろう。
ネガティブな記憶・体験は、自分が「うれしい」「楽しい」「良かった」と感じた記憶・体験で、上書き出来ると聞いた。それなら、わたしの傷も「ポジティブな痛み・傷」で上書きすれば、新たな一歩を踏み出せるのではないか。
一度「SMをしたい」という思いに囚われると、なぜこれまで挑戦してこなかったのかが不思議なほど強く引き付けられた。
けれども「実際に、その願望をどうやって叶えるか」を考え始めると、すぐに行き止まりに突き当たってしまった。
ネットで検索して、SMバーやSM愛好者達のオフ会、女性向けSM風俗、SMイベントの情報などを手に入れることは出来たし、SMに特化したマッチングサイトに登録することも考えた。けれども、胸のことを思うと、どうしても踏み出す勇気が持てなかった。
かろうじてSM風俗ならば、プロとして対応してくれるのではないかと思ったものの、見知らぬ相手とプレイするのは、やっぱりハードルが高く、なかなか申し込むまでには至れなかった。
***
考えあぐねていたある日、会社が引けた後、長い付き合いの女友達マキ・クミ・レナとの食事会があった。結婚が決まったマキを祝おうという趣旨で、四人でシャンパンを一本、ワインも三本空け、随分と酔っ払って帰宅した。
酔いを醒ましてから寝ようと温かいお茶を淹れ、なんとなく、スマートフォンでSNSを流し見しているときだった。
食事会で「婚活がめちゃくちゃ大変で、何度も諦めようと思った」と言いながらも、幸せそうに微笑んでいたマキの姿が、ふと脳裏に浮かんだ。
マッチングアプリに始まり、積極的に人に紹介を頼んだり、結婚相談所に入会したりと、彼女が頑張ってきた経緯を知っているから、心から祝福できた。しかし、その一方で、少し自分が情けなく思えてしまった。
恋人に「萎える」と告げられた時から、わたしは止まったままだ。そろそろ一歩、前に進まなくてはいけないのではないだろうか。
……けれど、どうやって?
突如襲ってきた焦りに突き動かされ、わたしはツイッターの検索窓に「SM プロ」と打ち込んだ。
ストリップ劇場でのSMイベントの告知、麻縄で緊縛された女性の画像、猫耳に首輪をして檻に入れられた女の子のイラスト……スクロールしていくと、目当てのアカウントに辿り着いた。
プロサディストを名乗り、SMプレイの依頼を受けている男性のアカウントだ。以前、そのアカウントを偶然見つけてから、ツイートを定期的にチェックしていた。
最初は「ちょっと、あやしいのではないか」と訝しんでいたけれど、たまに垣間見える彼のプライベートの様子からは、身元がしっかりしていることがうかがえた。それに、女性の生々しい裸など、そういう類のアダルトな投稿がないことにも安心感があった。
「どうせ、失うものなんて、ないんだし」
わたしはアルコールで高揚した気持ちをバネに、彼に申し込みのDMを送った。
***
こうして、わたしは彼と会うことになった。そして、SMを実現する相手として彼を選んだことは、この上なく正解だった。
本業が医療関係である彼は、医学の知識が豊富だった。さらに、乳腺専門医とも連携し、乳がんサバイバーのわたしがSMをする際の「医学的に注意しなくてはならないこと」を教えてくれたのだ。
「乳房がない」という見た目のことばかり気にしていたけれど、それ以外にも立ちはだかる障壁があることに、暗澹たる思いになった。しかし、彼は「一歩一歩一緒に進んでみましょう」と励ましてくれて、笑いながら少し泣いてしまった。
彼は、わたしの身体を慎重に扱ってくれた。緊縛ひとつとってもそうだ。
初回は、右半身と足だけ。二回目は、上半身すべてに縄をかけてくれたけれども、左半身には縄が触れている程度。三回目は、もう少しだけしっかりと。
そのように少しずつ進みながら、回数を重ねていった七回目。縛られて、天井から吊られることに成功した。
両足のつま先が宙に浮いたその瞬間、達成感が四肢に満ち満ちた。
「加虐は、僕からのプレゼントです。受け取ってください。」
ずっと動けなかったけれども、ようやく道が照らされた気がして、わたしは彼にこう告げた。
「次は、キャミソールをとった姿で、縛ってもらえますか」
あとは進むだけだ。身体を隠すためのキャミソールなんて、脱ぎ捨てて。
Episode 4 克服
明日の朝ごはんのパンと牛乳、今夜のお風呂あがりに食べる新作アイス。夫のヨウジの分とあわせて、これらを買い物かごに二つずつ入れたわたしは、レジカウンターに立っているのが「若い男性店員」であることに気が付き、思わず足を止めた。
――どうしよう。
緊張で身体が強張り、まるで金縛りにあったかのように、前へ進むことが出来ない。
このコンビニは初老の店長以外、店員はみんな女性だったはずだ。だから、初めて入る店では買い物前に必ず行う「レジ店員の性別確認」をしなかった。
買い物かごに入れたものを棚に戻して駅前まで引き返し、スーパーで買い直すという手もある。スーパーならば、並ぶレジを選べるから安心だ。
けれども、一度手に取った食品を棚に戻すことには抵抗があった。しかし、もし会計時に過呼吸を起こしてしまったら、もっと迷惑がかかる。
やっぱり、申し訳ないけれど、すべて戻してスーパーに行こう……と思った瞬間、彼の「命令」が頭をよぎった。
……行ける。行く。
わたしは背筋を伸ばし、レジに向かって一歩踏み出した。
***
三歳の時に両親が離婚し、父に引き取られたわたしが男性に恐怖心を抱き始めたのは、小学三年生の頃だった。
きっかけは、父が仕事を辞めて引きこもり、昼夜問わず酒ばかり飲んで過ごすようになったこと。酔った父は気性が荒くなり「テストの点が悪い」とか「部屋が散らかっている」とか何かと理由をつけて、わたしに暴力を振るってきた。
暴力は、家の中だけではなかった。
わたしはその頃から、男性による「性的な暴力」をやたらと受けるようになった。痴漢はしょっちゅうだったし、誘拐されかけたのも一度や二度ではない。
その理由は、今ならわかる。
明らかに大人に付けられた傷や痣が身体のあちこちにあり、日々のケアをしっかり受けているようにはみえない服装や外見の子ども――もっと言えば、誰からも愛されていないように見える子どもは、軽んじて扱っていい、好きに消費していいと、身勝手にも信じ込んでいる男達が存在するのだ。
けれども、そういうことに気が付いたのは最近で、それまで性的な被害に遭うことは、むしろ自分自身の内面に原因があると思っていた。
わたしの抱いている黒い願望――人とは違う性癖が、性犯罪者達の本能を刺激し、彼らを誘蛾灯のように引き寄せてしまっているのだ、と。
わたしの初恋は小学六年生で、相手は同級生の男の子だった。これが「普通の恋愛感情とは違う」ことは、既に自覚していた。
わたしが望んでいたのは、彼に縛られ、蹴られ、無理やりひどいことをされることだった。グループデートやファーストキスへの憧れを口にする同級生の女の子達とは、夢見ていることが明らかにまったく異なっていたから、誰にも言ってはいけないと思っていた。そして「こんなおかしな願望は、どうにかして消さないといけない」とも思っていた。
本当の欲望に蓋をしたまま、やがて高校生となり、ヨウジという恋人が出来た。
少し頼りないところはあるけれど、思いやり深い人で、父に暴力を振るわれているわたしの境遇に心を寄せてくれた。
高校を卒業した後もヨウジと付き合い続け、三十歳の節目で入籍した。
ただし、ヨウジは性的にはまったくのノーマルで、性欲自体が少ない人だった。わたしはわたしで、ヨウジには自分の性癖を伝えてすらいない上、普通のセックスは苦手で、出来るだけしたくない行為だった。
そのせいもあって、付き合ってすぐの頃からセックスレスだったけれど、夫婦としては何の問題もなかった。あの夜までは。
***
あの夜は、ヨウジが、会社の上司セイヤを家に連れてきた。酒を飲むと事前に聞いていたので、おつまみになるようなものを何品か用意し、メインはすき焼きにした。
セイヤは、ヨウジの二歳上の三十五歳だった。人当たりのいい男性だったこともあり、勧められて、わたしもお酒に口をつけた。最初は楽しく、会社でのヨウジの働きっぷりや世の中のニュースなどをネタにして、盛り上がっていた。
気が付けば、セイヤが持ってきてくれたスパークリングワインの瓶が空になっていた。それを機に、わたしはノンアルコールに切り替えようと、お茶を淹れるために立ち上がろうとした時だった。
「ね。あんたってさ、Мだよね」
何を言われたのか一瞬わからず、思わず顔をあげると、すっかり目が据わったセイヤの顔があった。目は怒りを帯び、口元は皮肉でも言うかのように歪んでいる。
わたしに暴力を振るう直前の、父の表情にそっくりだった。
「やめてくださいっ」と反射的に両腕を上げ、顔をガードしたところで、はっと正気に戻った。そろそろと腕を下ろし、必死に愛想笑いを浮かべる。
「セイヤさんってば。突然、どうされたんですか」
「なに、今さら誤魔化す気?じゃあ、ヨウジくんに聞いてみようかな。ね、ヨウジくん。君の奥さん、マゾでしょ、マゾ」
「え、ちょっと何を言っているのか……あ、俺、ちょっとトイレ……」
ヨウジは苦笑して立ち上がり、さっさと逃げてしまった。ヨウジは穏やかで優しい人ではあるけれど、こういうふうに何か不穏な空気が流れると、その場から逃げてしまう癖があるのだ。
「大分酔われてるんじゃないですか。お茶飲みます?お水のほうがいいですかね」
ヨウジの上司が酒乱とは知らなかったけれど、父の相手で、酔っ払いには慣れている。とにかく、少しでも酔いを醒まさせようと、水を汲むために立ち上がろうとしたその時。セイヤは手を伸ばし、わたしの腕をぐっと掴みあげた。
「い、いやっ!」
抵抗もむなしく、あっという間に抱き寄せられ、唇を塞がれる。
「ん、んっ!」
ジタバタと手足を激しく動かして抵抗するものの、セイヤはいとも簡単にわたしを強く押さえつけて両腕を拘束し、乳房を鷲掴んで言った。
「顔が物欲しそうなんだよ、あんた。いじめてくれって顔してる」
「やめ……やめてくださいっ」
咄嗟に身体を強くひねると、片腕が自由になった。その隙に、テーブルに置いてあったスパークリングワインの瓶を掴んで頭上に掲げ、勢いよく振り下ろす。
がつん、と手のひらに鈍い衝撃を感じた。と、わたしを強く押さえつけていたセイヤの力が抜ける。
「ヨウジくん、ちょっと、早く来て!大変だから……ヨウジくんってば!」
わたしはセイヤの元から必死に逃れると、叫んでヨウジを呼んだ。
***
この一件以降、わたしとヨウジの関係は微妙に変化した。ヨウジはわたしに負い目を感じているのか、どこかよそよそしい。一方で、わたしは、あの時に席を離れずに守ってほしかったという恨みがましい思いを抱いた。
けれども、夫婦の信頼関係をどうやって取り戻すかより、もっと重大な問題がわたしの身に起きていた。
それは、男性恐怖症の悪化だ。
病院、美容室、店のレジ、電車の中など、あらゆる場面で男性と身体が接触すると過呼吸を起こしたり、酷い時には嘔吐してしまったりすることもあった。会社の同僚男性とさえ話すことが出来ず、仕事に支障をきたすようになった上、自殺願望が抑えきれず、自傷することも度々あった。
このままでは、生きていけない。
けれども、わたしは生きたかった。自分を助けるには、どうすればいいのか。
出口を探して藻掻いていたある日、ツイッターで気になるアカウントを発見した。そのアカウントの主はプロのサディストで、依頼すれば、SMプレイをしてくれるという。
なんだか「あやしくて、いかがわしい」と思ったけれども、プロフィールに「M女性の夢を一緒に叶えることを目指している」と書かれているのを目にした瞬間、絶望に塗りつぶされていた心の中が、光で照らされたような気がした。
わたしに夢があるとすれば、好きな男性に加虐されることだ。ヨウジはSMはおろか、性的なことには興味を示さないし、男性恐怖症が悪化した今となってはますます叶わない夢だ。けれども……もしかして、彼なら叶えることが出来るんじゃないだろうか。
わたしは自身の状況を添え、彼に依頼のDMを送った。彼からは受諾の旨とともに「いくつか、主治医に確認してほしいことがある」と質問が届き、それに回答する形でやりとりを重ねていくうちに、約束のプレイの日が訪れた。
***
ホテルの部屋に現れた彼は、紳士的な男性だった。「プロサディスト」なんていう肩書きに身構えていたけれど、SNS上での印象そのままの穏やかな雰囲気でほっとした。
とはいうものの、見知らぬ男性とふたりきりでホテルの部屋にいるという事実は、相当な緊張をわたしに強いていた。部屋の中に招き入れてソファに座ってもらったものの、どうしても強く近くに寄ることが出来ない。部屋の入口に立った状態で彼と対面し、事前に伝えておいた男性恐怖症のことを、あらためて説明した。
「……こんなわたしでも、SMが出来るでしょうか」
説明が終わると、彼は頷いた後、プレイする上での注意点や「セーフワード」というプレイを中止する時の合図の言葉、リスクなどについて諸々説明してくれた。プレイ中の服装は着衣からスタートし、最も脱いだ状態でも下着までとすることを提案され、警戒心がわずかに緩んだ。
Mとしてプレイする以上、Sの要求はすべて呑まなくてはならないと覚悟してきたけれど、どうやら、そういうわけではないらしい。
大げさに身構えすぎていたことに気が付き、なんだかおかしくなって小さく笑う。すると、彼も穏やかな笑顔を返してくれた。
妙に和やかな雰囲気の中で、プレイが始まった。
彼の指示で、ベッドサイドに立つ。彼は、わたしから人ひとり分ぐらいの距離を取って、わたしと向き合った。
ヨウジ以外の男性と対面して耐えられる、ギリギリの間合い。彼はそこから手を伸ばし、ぐっとわたしの首元を掴みあげた。
途端、息が上手く吸えなくなり、後頭部がどくどくと脈打つ。
「んんっ……」
苦しさが、襲ってくる。
しかし、それは甘美な苦しみだった。いじめられているのに、安心感さえある。
うっとりと恍惚感に浸ったのもつかの間、どんどん手の力が強くなっていく。息苦しさが増していく中、彼は間合いを半歩ほど詰めた。
思わず、身体を硬直させる。
すると、首を絞めていた力が少し緩んだ。わたしの半開きの唇から吐息が漏れると同時に、気が緩んで足がふらつく。そのまま床に崩れ落ちそうになった私の身体を、彼は力強く、しっかりと受け止めてくれた。
男性の身体がすぐ近くにあることに拒否反応を起こす寸前、彼は再びわたしの首を締めあげる。今度は、一瞬で呼吸が止められてしまう。
咄嗟に、助けを乞うように彼の顔を見上げると、目が合った。
その静かな瞳の色を見た瞬間、不思議な安堵感を覚えた。彼は、わたしを傷つけようとして苦しみを与えているのではない。わたしが求めているから、苦しみを与えてくれていることを理解したからだ。
わたしにも、SMができた。
想像以上の充実感を得ることが出来た帰り際、彼はわたしに「命令」を与えた。
会社の同僚男性と話をしてみること。そして、話してみてどう思ったかを次に会った際に報告することが、わたしのミッションとなった。
翌日「命令だから」と自分に言い聞かせ、思い切って同僚男性に声をかけてみた。最初は、挨拶を交わすところから。次に、短時間の軽い雑談を交わす。
こういったことを経て、少しずつ長い時間話せるようになり、徐々に男性の存在を「脅威」に感じなくなっていった。
***
わたしは男性店員の手からお釣りを受け取ると、財布に仕舞った。心臓はいつもより高鳴っているものの、過呼吸を起こす様子はない。
「ありがとうございました」
店員の言葉に見送られて、店を後にする。
――「あなたを守り、背中を押すこと。それが僕の支配です。」――
あの日以来、彼とするSMは、わたしの「御守り」になった。男性恐怖症を克服して、前に進むための。
ProSadist Dr.N インタビュー(前編)
各Episodeの「彼」のモデルで、プロサディストとしての活動が五年目(公開当時/2022年)に突入したProSadist Dr.N。女性達に極上のセッションを提供するばかりでなく、SM研究を目的とした「SM Academy」の主宰や、オンラインサロン「Dr.N SM Lab」の運営なども精力的に行っています。
今回はそんなDr.Nの人物像に迫るべく、大泉りかがインタビューを行いました。彼の知られざる素顔に迫ります!
***
――この度は小説のモデルになっていただき、ありがとうございました。Episodeを提供いただいたM女性達の思いや事情を知り、わたし自身とても勉強になると同時に、Dr.Nという人間の奥深さを再発見することが出来ました。あらためて、今回の小説化プロジェクトへの思いをお聞かせいただけますか。
Dr.N 僕のプロサディストとしての活動も、二〇二二年で五年目を迎えました。りかさんから「これまでのDr.Nの活動でM女性に何が起き、どのような未来が拓けたかを小説化したい」と声を掛けていただき、M女性の目線で「プロにSMを依頼した経験」を描くとどうなるのか、僕も興味があったことから、プロジェクトがスタートしました。
本書の「はじめに」でも記したとおり、みんなで力を合わせた結果、非常に読み応えのある作品を作り上げることができました。
思春期に影響を受けたSM小説の世界。「いつかは自分も、小説の主人公のようなサディストになりたい」と憧れていたので、今は感無量です。外からは見えにくいプロの世界を、是非多くの方に知っていただければと思っています。
――本書の登場人物は、すべて実在の人物がモデルになっています。なので、Dr.Nや体験談を寄せてくれたM女性の方々から「全然違う、こんなのじゃない」と思われたら、どうしよう……と危惧しつつ、執筆したのですが……。
Dr.N 自分達が小説に登場することは夢のようで、率直に嬉しいです。各Episodeを読むと、あらためて当時のことが鮮やかに蘇ります。特に、M女性の心の中で、ひとつひとつの出来事がどのように感じられていたのかが言語化されたことで、M女性への感謝の気持ちがより強くなりました。
――本書の「彼」は、プロとして活動しているDr.Nがモデルですが、現実のDr.Nには「過去」と「未来」がありますよね。そのあたりをお聞きしたいと思っているのですが、まずはSMに興味を持ったきっかけや、プロのサディストとして活動するようになった経緯を教えていただけますか?
Dr.N 中学二年生の時、修学旅行先でSMのAVを初めて観たことをきっかけに、SMに興味を持ちました。
詳細は内緒ですが、京都の宇治駅で二本のAVを偶然入手し、夜、宿で同じ部屋の友達みんなで観ました。一本は普通のAVでもう一本がSMビデオでしたが、その内容が衝撃的だったんです。
――どんな衝撃を受けたのでしょうか。
Dr.N 多感な時期だったので、ノーマルなAVは、既に観る機会も多かったのですが(笑)SMのビデオは初めてでした……今でも、映像をはっきり覚えています。茶髪の綺麗な女優さんが緊縛されて、ケインや鞭みたいなもので叩かれて、叫んだり泣いたりしていて。とても刺激的でした。
その後、男友達と部屋にあった洗濯物を干すロープを手に、仲の良い女子の部屋に行って……お願いして、女子を縛らせてもらいました。
――えっ!即実行ですか!
Dr.N 「手足を縛ろうぜ、やってみる?」とお願いしたら、みんなノリノリで……ふざけて笑いながらの雰囲気でしたが、僕としては不思議な感覚というか「いいじゃん」って思いました。そこからスタートしました。
――お相手は?お付き合いしていた女性ですか?
Dr.N 最初は友達でした。その後、お付き合いしていた女性にもカミングアウトしましたが、それについては、ほとんど上手くいかなかったですね。
――お付き合いしていた女性には、性的な趣味を受け入れてもらえなかった。
Dr.N そうです。やんわりと拒否されました。結局、気まずくなり、破局するといった感じです。高校の時も大学の時も、同じような経験を繰り返すことになって「もう、やめよう」とSMを封印しました。
――M癖のある女性達からも、同じような悩みをお聞きすることは多いです。「SMがしたいけれど、恋人はノーマルなんです」など……。「プロサディスト」という存在は、こうした女性達にとっては、ありがたいと思います。でも、そもそも性的嗜好を封印することって出来たのでしょうか。
Dr.N 結論としては、出来ませんでしたね。二十代からはSMを封印し、普通の恋愛を六~七年続けていたのですが、いつも不完全燃焼な感じでした。
しかし、ある時、緊縛に興味のあるM女性に出会いました。自らを「M」と認識している女性に出会ったのは、実はこの時が初めてでした。性的嗜好について話す中で「じゃあ、ちょっと縄をやってみましょうか」となり、久しぶりに縄で縛りました。結果的に、僕自身ものすごく興奮したし、女性もとても喜んでくれました。その時「この世には、自分の性的嗜好を受け入れてくれる人がいる」ことがわかったのです。それまで僕がお付き合いしてきた方の性的嗜好はノーマルだったので、そもそも無理があったのだ、ということも。
この時、とても嬉しかったのと同時に「もっと上手くなりたい」と思いました。ずっと独学だったので、M女性とのSMや緊縛が怖くも感じました。「下手くそね」などと言われる気がして……そこで「教室でしっかり学ぼう」と決意しました。
――ああ、なるほど。それはS男性ならではの悩みかもしれません。
Dr.N それで三〇歳のときに、緊縛師の先生の教室に通い始めました。約二年で一通りの縛りを教えていただき、テストに合格することが出来ました。合格した日の夜は、先生がお祝いをしてくださいました。
お祝いの席で、先生に次はどうすればよいのかを相談したところ「M女性向けのSM風俗店を始めるから、キャストとして挑戦してみないか」というお話をいただきました。その時のことは、今でも鮮明に覚えています。
――とんとん拍子にプロに!プロとして活動するにあたり、不安やプレッシャーはありませんでしたか。
Dr.N 先生を信頼していたので、不安はありませんでした。別のお店だったら、挑戦しなかったと思います。先生は教室の運営もクリーンで、非常に厳しい方だったので、個人情報や将来的なことも含め、大きな信頼を置いていました。
プロとしての活動に関しても、SMの技能や知識、本業との兼ね合いなどをサポートしてくださり……先生に恵まれて、とても運が良かったと思っています。
――その先生のお店に二年所属し、独立して今に至ると……独立のきっかけについて、教えていただけますか。
Dr.N きっかけは、新型コロナウイルスですね。本業との両立が難しくなってしまったので、お店を退き、一年ぐらい活動を休止しました。その後、風営法の届出を出して、正式にプロとして復帰しました。
――満を持して、ですね。しかし、M女性をプレイの対象としたプロのサディストは、まだまだ珍しい存在です。性の現場では「女性」というだけで一定の需要があるので「なぜ、わざわざお金を払ってまで」という声もあるかと。SMの快感のエモーショナルな部分は「プライベートで親密な相手とのほうが、満たせるのではないか」と考える人もいるでしょう。
けれども、今回九名のM女性の体験談を読ませていただき、Dr.Nが、M女性ひとりひとりとしっかり向き合っている印象を受けました。
Dr.N ありがとうございます。僕は、才能やセンスがあってプロになったというケースではありません。すごく悩み苦しんだ結果、ひとつひとつ学ぶことで道が拓け、プロになりました。
急展開で、こうなることは想像もしていませんでしたが、多くの機会に恵まれたことに感謝しています。
しかし、だからこそ「お会いするM女性にも、似ている方がいるのではないか」と考えました。プロとして活動していく中で出逢うM女性は、みなさん何かしらの思いを抱え、自分なりに乗り越えようとしているように感じます。そこには「誰にも打ち明けられずに」といった悩み・苦しみだけでなく「もっと楽しみたい」などの切実さもあり……多かれ少なかれ「SM」に特別な思いを持っているように感じました。こうした意味で、僕と似ている方も多くいらっしゃいますし、僕の経験を還元していく形でプロとして活動することが、僕に合っているんだと実感しています。
――小説化する中で最も驚いたことは、すべての体験談で「前向き」が共通のキーワードになっていたことです。SM小説って、女性が堕ちて終わるパターンが定番のひとつだと思うのですが、そこがまったく違うなって。
Dr.N ありがとうございます。SMに対して、そして自分に対して「前向き」になる。まさに、僕が先生の教室や在籍したお店の研修で学んだことです。僕自身がSとして、習ったこと、学んだこと、実践したこと、体験したこと、人と対話することで前向きになれた。それが大元にあるからだと思います。
例えば「わたしがMに生まれてきたことが原因で、こんなに不幸になっている」とおっしゃる方もいらっしゃいます。しかし、よく話を聞くと、性的嗜好が直接マイナスに働いているわけではなく、それを受け止めてくれる人がいない孤独感や共感を得られにくい疎外感、差別・偏見・迫害といった周囲の誤解がマイナスに働いたことが原因になっているケースが多いのです。だからこそ、僕はSMを良い形で共有できる人間が現れれば、自然と前向きになっていけるのではないかと考えています。
(後半に続く)
Episode 6 克己
ショーの出番を終え、楽屋で私服の黒のワンピースに着替える。私は昂りの余韻を抱えたまま、フロアのバーカウンターに足を運んだ。
「お疲れさま。何か飲む?」
「ラムコークもらえますか?」
顔見知りのバーテンダーからラムコークの入ったグラスを受け取り、客で誰か知り合いが来ていないかとフロアを見渡す。
このバーで毎月一度開かれるSMショーに、モデルとして出演したのは今日が初めてだった。けれども、こういったフェティッシュなイベントの常連である知り合いは少なくないから、今日も誰かしら来ているのではないかと思ったのだ。
しかし、知り合いを見つける前に、突如声を掛けられた。
「あの、先ほどショーに出られていた方ですよね」
振り返ると、スーツ姿の見知らぬ中年男性が、ロックグラスを手に立っていた。
「あ、はい。そうですけど……」
「いや、なかなか良かったですよ。色が白くて赤い縄が映えるし、肉づきがいいから、肌に食い込む感じなんかもね。ものすごくセクシーだったかな」
男は舐めまわすように、わたしの身体に視線を這わせた。もちろん、褒められることはありがたいけれど、今回はセクハラじみていて思わず身構える。しかし男はわたしの内心など気に掛ける様子もなく、続けて言った。
「前回のショーのモデルさん、名前なんだったかな。あの人はハードでね。彼女に比べると、あなたは、ちょっと責めを受け切れていないところはあるけどね」
なぜ、見ず知らずの男から、ショーのダメ出しをされなくてはならないのか。しかも、他のモデルと比べる形で。むっとしたのが顔に出てしまったのか、男は感じ悪く口元を歪め、厭味ったらしい口調で続けた。
「期待外れとまでは言わないけど、ちょっと正直。まぁ、これからも頑張ってくださいね」
「はぁ……」
男は言うだけ言うと、さっさとその場から去っていった。ひとり取り残されたわたしは、甘ったるい炭酸のお酒をごくりと飲みほした。
***
わたしがSMショーのモデルを始めて、二年になる。
きっかけは、興味があって出入りしていたボンテージ系のイベントで知り合ったオリエというミストレスに「SMが好きならモデルをしてみないか」と誘われたことだった。
それまでも、プライベートでSMをする男性がいたことはあるし、SMクラブでMのキャストとして働いていたこともある。もともとSMはずっと好きだったし、SMがない人生というものを考えたことすらない。
そんなわたしにとって、SMショーのモデルの誘いは、ひどく魅力的であった。
とはいえ、ふたつ返事で了承できるわけでもなかった。それまで、わたしはアートやパフォーマンスといったものとは、まったく無縁の人生を送ってきた。表舞台で何かを表現するなんて、想像したこともなかったからだ。
けれども、今回の誘いを見送れば、もう二度とこんなチャンスはないだろう。断ると、必ず後悔すると思った。
そうして散々悩んだ末に、わたしの背中を押したのは、誘ってくれたオリエとわたしのSM観がとても似ていたことだった。
「オリエとタッグを組み、自分の思うSMを表現してみたい」という切なる願いから、わたしはSMショーのモデルとなることを決意したのだった。
SMショーのモデルとしてステージに立つのは、想像以上に刺激的だった。
始まる直前には、吐き気を催すほどの緊張感に襲われる。けれども、一旦ステージの上に立つと、目が眩むような照明と大音量の音楽が、あっという間にわたしを恍惚へと連れていった。
肌に擦れるロープと、蝋燭の溶けるにおい。苦しさの中で生まれる甘美。ショーの最中、わたしは歓びに満ちていて「人生が変わった」とまで思った。
しかし、ステージでのパフォーマンスを純粋に楽しめていたのは、最初の半年だけだった。出演回数を重ね、幾ばくかの余裕が生まれるにしたがって、わたしの中の葛藤がどんどん大きくなっていった。
これまでのSMは一対一、相手と自分だけで完結するものだったから、プレイ中は相手に集中していればよかった。相手の嗜虐心を満たしつつ、こちらの被虐心を満たすのは、それほど難しいことではなかったし、たとえ「なんだか今日はしっくりこないな」と思う時でも、いくらでも調整して、互いが納得するプレイを楽しむことが出来た。
けれども、ショーの場合は身体を使って表現し、ステージの下にいる観客達を満足させなくてはならない。
初めて味わう、観客の視線に晒されるという経験。しかも、彼らは金銭を支払って、わたしたちのショーに臨むのだ。当然、批判的な視線だって生まれる。
ショー終了後に寄せられる、無責任なアドバイスやクレーム。最初は受け流していたそれらが、わたしの心をじわじわと蝕んでいった。
観客達が求めているのは、エロスなのか。それとも、これまでに観たことがない過激なパフォーマンスなのか。
「彼らが観たいものを表現しなくてはならない」という義務感に囚われ、わたしは次第に、自分の欲望がわからなくなってしまった。
***
自分を見失いながらもステージに立っていたある日、わたしはまったく楽しめていないことに気が付いた。縛られても打たれても無感動で、ただ機械的な声を漏らすことしか出来ない。
「やっぱり、向いていなかったんだ」
その瞬間、ステージの上にいる自分が、とてつもなく恥知らずに思えて泣きたくなった。
ショーをぶち壊してはいけないと思い、なんとか最後まで必死に耐えたものの楽屋でわたしはオリエに訴えた。もう、ショーに出るのは無理かもしれない、と。
「無理することはないけど、今やめたら、SMが嫌いになっちゃうんじゃない?」
「でも、わたしが表現したかったSMは、お客さん達には認めてもらえない……それじゃ、やってる意味がないんです」
「やってる意味がない、なんてことはないから。今すぐに決めなくてもいいからちょっと冷静になってみたら。ね。今日は無理して残っていないで、もう帰ってもいいし。それとも、お酒でも飲む?」
「……いえ、今日は帰ります」
わたしが荷物をまとめ終わるまで、オリエは心配そうに見守っていてくれた。
「またね。ゆっくり考えて」
「はい……」
楽屋を後にしながら「オリエと一緒にショーをするのも、今夜が最後かもしれない」と思うと、寂しさのようなものが押し寄せ、嗚咽してしまいそうだった。
それから数日間、わたしの脳裏にはオリエの言葉がこびりついたままだった。
「SMが嫌いになる」
そんなことを考えたことは、これまで生きてきた中で一度もなかった。けれども、最後にステージ上でしたSMに、わたしが楽しさをまったく感じられなかったのは確かだった。
それでも、やっぱり、SMで感じる歓びを失くしたくない。
わたしは、これまでSMを通じて知り合った友人達に相談を持ちかけた。
「たまたま、ショーという形式が合わなかっただけで、またプライベートで楽しめばいい」と言う人もいれば「無理してすることでもないし、また自然としたくなる時が来るんじゃない?」と慰めてくれる人もいた。けれども、プライベートでSMをする相手を見つけるのだって、それなりの労力がかかる。
もし見極めを誤ってプレイの相性が合わない人としたら、ますますSMを敬遠することになってしまうかもしれないと考えたら、二の足を踏むのに十分だった。けれども、自然と欲求が湧くまで待つのは、じれったくて耐え切れないと思った。
そんな中で、ひとり「プロのサディストがいるらしいから、試してみたら?」と提案してくれた女友達がいた。その人はSNSで、プレイを希望する女性を募っているという。
教えてもらったツイッターのアカウントの投稿を遡って読んでいくうちに「この人なら、大丈夫な気がする」と不思議な確信が湧いた。それに「プロに頼んでダメならば、あっさり見切りを付けられるだろう」という気持ちもあった。
***
プレイをするにあたり、プロサディストだという彼に、わたしの経験値をどこまで話せばいいのか悩んだ。なんらかの先入観を持ってプレイされるのは嫌だけど、一方で「まったくの未経験である」という嘘を吐きとおせる自信もない。
結局「少し経験があるものの、何が好きかはわからない」という、なんとも中途半端な自己紹介をした。その後、彼は縄や鞭、スパンキングなど、オーソドックスなプレイをひとつひとつ丁寧に試してくれた。
ショーの最中はいつも慌ただしかったし、わたしの好き嫌いより「観客に何を観てもらうか」が最も重要だった。
だから、ひとつひとつの行為を「このプレイは好き」「このプレイは嫌い」「このプレイは嫌いじゃない」などと考えるのは久しぶりだった。そして「嫌い」と感じたプレイでも、彼の触り方や打ち方によって「好き」に変わることに驚いてしまった。
彼の手にかかると、嫌いなプレイが、どんどん好きになってしまう。まるで治療されているようだった。
終わった時、わたしは「SMが大好きだった自分」にすっかり戻っていた。
***
「わたし、実はSMショーのモデルをやっていたんです」
彼にそう打ち明けたのは、三度目に会った時だった。ずっと言わないでいるのも、どこか後ろめたい気がしていたし、ずっと抱えていた「ある悩み」について彼ならば解決の道筋を示してくれるのではないかと思ったのだ。
わたしの悩みは「SMショーでは観られることを意識しすぎて、楽しめない」ということだ。「それらしい表情を作らなければ」という義務感に囚われ、どうしても快感に辿り着けない。プレイに入る前に、そのことを思い切って伝えてみた。
すると、彼はiPhoneのFace ID(顔認証)を使ったプレイを提案してくれた。プレイ中、わたしは表情を作ることに努めて「iPhoneのロックの解除を目指せ」と言うのだ。
わたしには到底思いつかないユニークな提案だと思うと同時に、負けん気が刺激された。一応は、プロの端くれとしてステージに立ってきたのだ。なんとしても解除に成功して、エセではないことを彼に知ってもらいたい。
けれども、一方では、不思議なことに「敗北して、打ちのめされたい」という気持ちもあった。
プロとしての意地と、屈服させられたい被虐的な願望。そのふたつが複雑に混じりあったまま、彼に身をゆだねた。
彼の鞭での責めは、これまでに経験したどんなプレイよりも激しかった。
わたしは絶叫し、悶え、どろどろになるまで泣いた。表情を作る余裕なんて少しもなくて、結果的に、わたしは一度もロックを解除出来なかった。
ショーモデルとしてのプライドは、ずたずただったけれども、わたしの気持ちは妙に爽快だった。
そんなわたしを見て、彼がくすりと微笑んだ瞬間、ふと思った。彼は最初からそうなることをわかっていたのではないかと。そして、彼は言った。
「過去の経験がどうであれ、僕は「あなたとのSM」をゼロから創りたいと思っています」
その後、わたしは彼に背中を押される思いで、SMショーにカムバックした。
***
甘ったるいお酒が喉を滑り、胃に落ちると、再びフロアを見回す。すると、先ほどの批評家気取りの男が、オリエと話しているのが目に入った。
いつもにこやかに微笑んでいるオリエが、珍しく真顔だ。きっと、あの男はまた、ゴミみたいな「俺様のSM論」を語ってでもいるのだろう。
わたしには、わたしの思うSM観がある。
それはまったく間違っていないことを、プロのサディストとして活動する彼に教えてもらった。いや、そもそも間違った価値観なんてないのだ。
それぞれの価値観があって当然で、それをどう表現していくかも、それぞれの自由だ。
わたしはオリエ達の元へまっすぐ歩み、男の肩を叩いて、きっぱりと言った。
「わたし達は、わたし達のSM観を表現したくて、ステージに立ってるんです」
男はあっけにとられたように、口をぽかんと開けた。その隣で、オリエが手を叩いて大笑いしている。
私は誇らしげな思いで、嫌いになりそうだったSMを再び好きにさせてくれた彼に、心の中で告げた。
わたしはSMを諦めずに、続けていく、と。
ProSadist Dr.N インタビュー(後編)
――後半ではDr.Nの「未来」についてお聞きしたいと思っています。まずはどのようなことに取り組んでいきたいか、教えてください。
Dr.N 僕は常に「M女性の夢を一緒に叶えること」と「一流のサディストになること」を目指し、活動しています。さらに「SMを科学する」という大きな目標もあります。これらの実現に向け、日々の練習、勉強、研究、実践、そして自分を磨くことを継続していきたいと考えています。
話は少し変わりますが、性的マイノリティに対する価値観は、時代と共にアップデートされています。例えば「LGBTQ+」は従来の「男女」の性別や、これまで当然視されてきた文化・法制度を根本的に問い直す中で、理解・受容が進んでいます。また、風俗やAVをめぐる環境も、倫理観の変遷に伴い、よりクリーンになるように法律が見直されています。当事者がよりよい生活を送れて不幸にならないように、社会全体で論理的・科学的な議論が行われる中で、徐々に改革が実行されてきました。
話を戻すと、僕は、近い将来SMでも同じことが起きるのではないかと考えています。つまり、大きな問題が起きた時や何かのきっかけで、どこまでを趣味や性的嗜好として受け入れ、犯罪や病気と線引きするか――日本社会が、SMをどのように位置付けるのかの議論が始まると思っています。その時が来たら、僕は「参考資料」として、科学的・客観的な事実を根拠とする研究資料を提出したいと考えています。僕の周りのSM愛好家達が不当な扱いを受けず、継続的にSMを楽しめるように。
――なるほど。SM研究の目標は、そこなんですね。
Dr.N はい。もちろん第一は「ご依頼くださったM女性に、よりSMを楽しんでいただくために」です。しかし、その先には、僕や周囲のSM愛好家達がいずれ遭遇するであろう、根本的かつ大きな課題があると考えています。
現在はSMを科学的に捉えた資料が少ないため、文化的な観点から「今までは●●だった」という話しか出来ないと思います。そこで僕は「日本や世界ではSMをどのように研究し、どのように解釈しているのか」を考察し、さらに生理学や解剖学、医学、健康科学、心理学、心身科学などの視点から「SMとは何か」について、科学的に説明できるように整理していきたいと考えています。
実は、これらは既に、僕と同じような志を持つ仲間達で立ち上げた「SM Academy」という団体において、各種研究・活動を進めています。本団体は【Quality of SM Life】&【Creates wisdom of the SM】をコンセプトに、SMの質の向上を目指し、SMの知恵を創造しています。「みんなで楽しくSMを学び、研究する」ための、完全紹介制の有料オンラインアカデミーです。
――まさに、先程の「SMを科学する」活動といえますね。こうした研究においては、Dr.N自身がプレイヤーでもあることが、ひとつポイントになっていると思いました。Dr.NのSM観や実際にSMをする際のスタンスは、どういったものなのでしょうか。
Dr.N 僕のSM観は「思いやり、コミュニケーション、合意、注意、安全」を心がけて「自律的、自立的、建設的、健康的」な関係を目指す。その上で「愛情、想像、優雅、感動、共鳴」をコンセプトに「加虐は僕からのプレゼント」という思いを形にする、というものです。
――このSM観は、何かに基づいて作られたものなのでしょうか。
Dr.N 「思いやり、コミュニケーション、合意、注意、安全」という考え方は、アメリカのBDSM研究の4Cs(思いやり〈Caring〉、コミュニケーション〈Communication〉、同意〈Concent〉、注意〈Caution〉)というモットーを参考にしています。4Csは、SM愛好家とSM研究者が議論してまとめたモットーという研究の中で開発された概念になります。
「自律的、自立的、建設的、健康的」な関係を目指すというのは、心理学における心理カウンセリングの要素を参考にした概念です。そして「加虐は僕からのプレゼント」は、プロとして活動する中で気付き、大切にしている思いです。
――具体的に、どうやって実践しているのでしょうか。
Dr.N 「思いやり、コミュニケーション、合意、注意、安全」は、M女性との対話やプレイ、その他すべてにおいて常に意識しています。
「自律的、自立的、建設的、健康的」な関係については……世間では、SMに「依存的、他律的、破壊的、病的」な関係をイメージされている方もいらっしゃると思います。確かに、こうした関係が性的満足・性的嗜好に反映されている方もいらっしゃいますが、これは一歩間違えると非常に危険なことでもあると思います。そこで僕は反対の関係を持つことで、日常生活に支障をきたさず、あくまでも健康的な範囲で楽しめるようにバランスを保つことを心がけています。
――確かに、世間ではSMに対し、そういった「ネガティブなイメージ」を抱いている人は多そうですね。
Dr.N 依存も他律も破壊も病的(あくまでも的な範囲)も、適度かつ短時間であれば、性的満足・性的嗜好に反映してもよいと思います。ネガティブな四つの要素をSMにおいて実現することで、日常に戻った時にはそれが満たされ、不要になっている状態になっていることもあるでしょう。しかし、終わった時には「自律的、自立的、建設的、健康的」に戻す必要があります。
――なるほど、SMに興味があり、やってみたいと思う一方で「洗脳されたらどうしよう」「依存してしまいそう」などと考え、踏み込めない女性もいると思うのですが、そういう話をしてもらえると安心です。
Dr.N もちろん、危機感は持っていた方がよいと思います。もう少しわかりやすく言うと、依存については「すべてがダメ」というわけではなくて「依存が一カ所に集中するとおかしくなってしまう」ということです。僕は、SMで依存を一時的に楽しむことと、日常生活で何かに依存しきってしまうことは、まったく異なると思っています。
例えば、遊園地に行った際、ジェットコースターで一時的に恐怖を楽しむのは問題ありません。それが、日常生活でも「常にジェットコースターで移動したい。交通手段はジェットコースターでなければ」と求めてしまうようになると……危ないですよね。ゆえに、SMで一時的にネガティブな要素を「楽しみ」として味わい、満足することで日常生活がより良くなるなら、問題はないと思います。
――ありがとうございます、よく理解できました。それから、最後にあげられた「加虐は僕からのプレゼント」というのは、素敵な思いですね。
Dr.N 僕がM女性と向き合う中で大切なことを三つ学び、この思いに至りました。第一は「自己一致」です。これは、自分自身がありのままの感情を体験して受容していること。自分自身を欺かず、純粋でいることです。自分自身がM女性に対して偽りがあると、お相手を悲しませてしまいます。一緒に過ごした時間やSMでの表現が偽りにならぬよう、真摯に本気で向き合うことが大切だと気付きました。
第二は「無条件の肯定的配慮」です。これは、価値観や好みを押し付けることなく、またSM以外で条件を付けることなく、自分とは異なる「ひとりの人間」として肯定的な配慮や積極的な関心を向けることです。SMをどのように解釈しているか――SM観は個々で異なります。お互いを尊重しつつ、M女性の言動に関心を持って、肯定的に関わることが大切だと気付きました。
第三は「共感的理解」です。お相手のM女性が持つSM観を、可能な限り自分自身のもののように捉え、それを伝えるように努めることです。異なる価値観をすべて自身のもののように捉えることは、僕達が別個の人間である以上、難しいことです。あくまでも、可能な限りにはなります。しかし、共にSMを行う上では、この共感が大切だと気付きました。
僕は「自己一致」「無条件の肯定的配慮」「共感的理解」を込めて加虐を行っており、これを一言で「加虐は僕からのプレゼント」と表現しています。偉そうなことを言っていますが、実は、この考え方は「心理カウンセラーがどのようにクライエントに接するべきか」という議論の中で、アメリカの心理学者カール・ロジャーズが提唱した知見を応用したものです。
――世間では、SMは文学やアートで語られることが多かったので、心理学や医学ベースの話は、すごく新鮮です。ここまで、SM観やスタンスについてお聞きしてきましたが、Dr.Nが特に好きなプレイは、どんなプレイなのでしょうか。何をしている時に、一番興奮しますか?
Dr.N 結論から言うと、僕は特定のプレイというより「SMそのもの」が好きです。僕はSMには刺激に関する「六つの要素」があると考えています。第一はディプロイメント。配置、展開です。第二はリレーションシップ。人と人の関係性、SMの特殊な関係性です。第三はアクティビティ。プレイ内容です。第四はコンテクスト。前後関係、背景、文脈、状況、脈絡、環境です。第五はツール。身体を含めたお道具と手段です。第六はスティミュレーション。刺激そのものの質です。これら六つの要素を組み合わせた加虐によって現れる「僕しか知らない、あなたの本質的な反応」が見えた時に興奮します。
――なるほど。だからこそ、様々な願望を持つM女性に寄り添い、それを叶えることが出来るのですね。では、最後に、今後の目標を教えてください。
Dr.N 僕は、常に「M女性の夢を一緒に叶えること」と「一流のサディストになること」を目指し、活動しています。現在はまだまだ至らないので、先程お話ししたとおり、まずは「自己成長」が目標です。日々の練習、勉強、研究、実践。お相手を知り、自分を磨くことを継続していきたいと考えています。
そして、その先には「城を手に入れる」という目標があります。SがよりSでいられるように、MがよりMでいられるように、SMの最高の空間を作りたいと思っています。この体現として、SMをコンセプトとしたリゾート施設、パーティー会場、研究施設、医療施設などを備えた「SM複合施設」として城を建てたいと考えています。
あとは「全国展開」です。僕は毎年、各主要都市でSMツアーを行っています。この背景のひとつには「地域格差をなくしたい」という思いがあります。地方は都心部と比較して、身バレや選択肢の少なさが課題になっているように感じています。そこで、蛇口をひねれば水が出るように、スイッチを押せば明かりがつくように「オーダーをすればプロサディストがやってくる」ことを叶える、全国組織を作れたらいいなと考えています。
今お話しした「自己成長」「城」「全国展開」の三つが、今後の僕の目標です。目標の実現に向け、これからも様々なことに挑戦していきます。みなさん、是非応援とご協力をいただけると幸いです。
――本日はありがとうございました。
(聞き手=大泉りか)
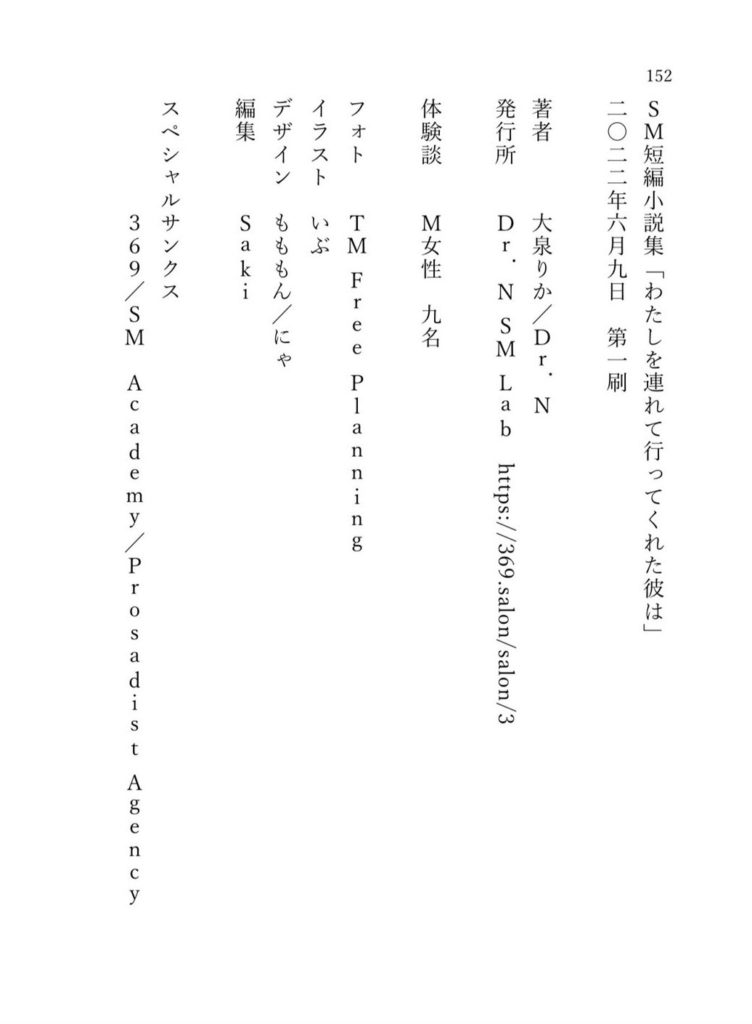
ProSadist Agencyの公式ECサイトからご購入いただけます。(製本版/ダウンロード版)